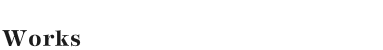
memory - Tachikawa air base
2008年 タイプCプリント
斎藤美奈子 - 遠さの加減
李 美那 / 神奈川県立近代美術館主任学芸員
昨年10月の斎藤の個展「Memory-かみの橋」を訪れてから、遠さということが頭を離れなくなった。
100cmを超える大きな正方形のパネルに、周囲に白い空間をとって風景の写真が焼き付けられている。映っているのは川、橋、原、雑草、電線、雲、これといって特徴のある景色ではない。目を引く建物も強い色もなく、人もいない。どこを見ていいか、しばらく途方に暮れるような、漠とした写真である。が、どれも空が広い。そして光を感じる。これを撮る、という明確な対象は写っている物にはなくて、写った木、雲、空、陽の光や残された何も無い空間が緩やかにからまって、ある空気の感触が現前する。
もう一回り小ぶりなものもあわせて、大小の風景が、ゆっくり歩いて一歩半くらいの距離をおいて続く。写真にはスポットライトが当てられているのだが、四角い写真が自ら発光しているような感じだ。部屋の奥には、かつてのミシン台であろうか、古い机と丸椅子がひと組。古びた布が、半ばやりかけの感じで机上に広がっている。布の上には若い女性の赤茶けた写真が乗っていた。壁も床も、もののあるところに照明の光溜りがあるだけで、あとの空間は暗く静かに沈んでいる。壁の写真と周りの空間の境界がゆるんで、風景の抱えている空気が外まで流れ出す。
既知と未知のないまぜになった、眼前の光景はそのままに異次元にいるようなゆらぎ。矛盾しつつもその底に感じる確かな現実感。写真だけではない、わずかなしつらえの全体、それが呼び起こすこれらの感触が、斎藤の作品の姿だろう。
「かみの橋」のきっかけは、母の急逝である。会場をゆっくり一巡して後、作家から、写真の場所は亡き母が見たはずの風景であると聞き、机上の布は、洋裁を学んだ母の充実した若い日々の品である、と聞いても、写真からも空間からも、安易な親近感は感じられなかった。感じるものは、方向を少しく異にしていて、周囲のすべてが自分の身からはるか遠くへと引いていく、自分自身すらも遠ざけようとしているかのような、遠ざかる感覚であった。
斎藤の初期の作品には、どこかに社会的弱者や歴史解釈にまつわる見解の表出が少しづつ滲んでいて、作品と作者の存在は表裏一体に近かった。その頃、写真はしつらえの中の一つのツールにすぎなかったように思う。数年前からのMemoryシリーズの初期、精神病院の窓を撮った作品のあたりから、基本的に目撃記録装置であるカメラを、目撃することから自らをずらすための身体的プロセスの一部として使い始め、写真であることの意味が重くなったのではないだろうか。2006年の妻有のトリエンナーレ、昨年の個展と、この関係性の変化は急速に進んでいるように見える。
斎藤の写真の底には追体験の構造がある。特にMemoryのシリーズにはその傾向が色濃い。精神病院の窓から窓枠ごしに外を撮った時には、その窓から外の景色を見たであろう患者の行動をなぞってみている。雪原に立つ枯れ木の写真では、妻有の豪雪地帯に嫁いだ女の生涯を幾晩も聞き、彼女の歩いた雪道を歩いてみる。「かみの橋」ならば母のかつての住まいを捜し、古い友人を尋ね、自分と縁のできる以前の母の人生を拾い集めてみる。その都度、斎藤自身はかなりの深みにまで、対象とした人間の気持ちや状況によりそい、時にはこれ以上は自分が壊れてしまうと思うほどに真摯に向き合う。そしてその人の眼をたどって、ある風景を訪ねて行く。
しかしそこで、斎藤は目撃の記録を撮らない。対象となる人の眼から出発して、一度はそれを自分の目で重ね、そこからぐるっと螺旋状に一回りして、同じ風景が違う風景になる瞬間を時間をかけて探る。写真を撮ることで、自分の身から一度得たものを引き剥ぐようにして遠ざける。追体験は制作プロセスの底に沈み、さらに今では、全体としての強い感触にもかかわらず写るもの自体は漠としているように、自分の眼に写っているものすら、写った写真から遠ざけようと努力しているかのようだ。遠さはだんだんと進み、「かみの橋」では、出発点は母というこれまでで最も身近なものでありながら、写真の遠さの加減は最も遠いと感じるところまで来た。そしてしつらえは、遠ざかる写真をかろうじて出発点につなぎとめ、作品全体の遠さの振幅を広げている。
過去へ遡れば遡るほど、はるかな未来を感じることがある。遠さの加減は遠ざかることだけを意味しはしないだろう。その加減の具合を見に、今回も足を運ぶことになりそうである。



